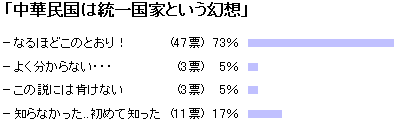| Reconsideration of the History |
| 109.国家主権不在の乱世 ── 統一国家「中華民国」の幻想 (2002.11.21) |
|---|
前回のコラム(108.「中華民国」は清朝の後継国家では無い)で、「中華民国」について少し触れましたが、この「中華民国」と言う存在も実の所、相当な曲者(くせもの)としか言い様が無く、1912(明治45)年の成立から1949(昭和24)年の台湾移転迄、日本は良くも悪くも、この「中華民国」に振り回され続けたと言えます。では、何故、日本はそれ程迄に振り回され続けたのか? 実は、「中華民国」が厳密には到底「国家」とは言えない存在だったからなのです。と言う訳で、今回は「国家」であって「国家」で無かった「中華民国」について書いてみたいと思います。
「国家」であって「国家」で無い? この様に書くと、皆さんは不思議に思われるかも知れません。何故なら、皆さんは恐らく近現代の「中国史」について、こう教わったからです。すなわち、
清朝(清国)→中華民国→中華人民共和国と国家が変遷したと。確かに、清朝は辛亥革命に伴って宣統帝・溥儀が退位する迄、皇帝を中心とした統一政府(朝廷)によって統治されていましたし、現在の「中華人民共和国」も共産党を中心とする一党独裁政府によって全土が統治されています。では、「中華民国」はどうであったのか? 問題の本質は正にここにあったのです。
「中華民国」成立の原動力となった辛亥革命でしたが、原動力になったと同時にこの辛亥革命によって「中華民国」は苦しめられました。一般に「辛亥革命」と言うと、1911(明治44)年の武昌蜂起から翌1912年の清朝滅亡・「中華民国」成立を指して使われますが、実際には、1913(大正2)年、江西・安徽・湖南・広東・福建・四川と言った諸省が袁世凱大総統に反旗を翻して独立を宣言した第二革命、1915(大正4)年、唐継堯等の帝制反対派が皇帝即位を画策した袁世凱に対して雲南省独立・護国軍(討伐軍)を組織した第三革命と三期に分けられ、「辛亥革命」は清朝打倒よりも、「中華民国」成立後に費やした時間の方が大きいのです。それでも、その「辛亥革命」によって支那国内が安定し、統一国家として歩めば何ら問題はありませんでした。しかし、情勢は更に混乱していったのです。
1916(大正5)年1月1日、大総統として権力の頂点にあった袁世凱は、内外の反対を無視する形で強引に皇帝即位式を挙行、元号を洪憲と定め、「中華民国」改め「中華帝国」の成立を宣言しました。しかし、日本を含む列強諸国は改めて、袁「皇帝」に対して帝制延期(無期限延期)を勧告し、国内に於いても諸省が反袁独立を図った為、袁「皇帝」は、即位から僅か22日にして帝制を断念し「退位」、同年6月6日、失意の内に病没したのです。しかし、この袁世凱の死が「中華民国」の混乱に更なる拍車を掛けたのです。
色々と悪評が高い袁世凱ですが、彼が清朝と孫文等の革命政府を仲介し、曲がりなりにも「中華民国」を成立させたのは事実ですし、英国を始めとする当時の列強諸国が彼の実力を評価し、支那の新しい指導者(大総統)として認め、一刻も早く混乱の中にあった支那の政情が安定する様に支援したのも又、事実です。(「中国革命の父」と称される孫文は、列強諸国から「孫大砲」(大ホラ吹き)と揶揄され、信用されていなかった) 惜しむらくは、彼自身が権力に欲が眩(くら)んで「共和制」を廃止し、内外の猛反対を無視する形で自らを皇帝とする「帝制」復活を企てた事位でしょう。しかし、裏を返せば、袁世凱が自他共に認める実力者だったと言う事でもあり、彼の死がもたらしたものは余りにも大き過ぎました。それは、「中華民国」と言う巨大な樽を締めていた「たが」(袁世凱)が外れた事を意味し、最早、巨大な樽は二度と樽としての形を取り戻さなかったのです。
袁世凱の死後、「中華民国」は最早、誰にも収拾が付けられない乱世へと突入してしまいました。元々、「中華民国」は、成立直後から各省・各有力者がてんでばらばらに行動する風潮が強く、何かと言うと、やれ二言目には直ぐ「独立」を宣言する様な状態だったので、強大な権力者だった袁世凱をしても、纏(まと)め上げる事は非常に困難だったのです。そこへ持ってきて袁世凱の死です。こうなると、もう誰にも止められません。各省が次々と独立を宣言し、好き勝手に「政府」を組織する始末。又、「中華民国」には中央政府の管理下に置かれた統一軍等無く、各実力者が私兵を抱える所謂「軍閥」なるものしかありませんでした。その軍閥が自分達の勢力を広げ、「中華民国」における主導権を握ろうとして「しのぎ」を削り、安直戦争(安徽派・直隷派)・直奉戦争(直隷派・奉天派)と言った軍閥による内戦状態へと突入していったのです。
その後、「軍閥」による「内戦」は、「孫文の後継者」を自認する蒋介石が、国民革命軍を率いて二度にわたる「北伐」(1926〜1928)を行い、1928(昭和3)年6月9日、北伐軍の北京入城を以て「北伐」は完了、蒋介石が支那の新たな指導者と認知される所となったのです。しかし、その一方で、支那国内にも1921(大正10)年、共産党が組織され、1931(昭和6)年には福建省瑞金に毛沢東を指導者とする中華ソヴィエト臨時政府(所謂「瑞金政府」)が発足する等、情勢は単なる「軍閥内戦」から、「支那の赤化」(共産化)と言う要素も加わり、益々複雑化していったのです。
1937(昭和12)年、共産党によって画策された廬溝橋事件が発端で、日支(国民党)両軍は戦闘状態に突入、所謂「支那事変」(日華事変・日中戦争共呼ばれる)が勃発しました。その後、両軍は停戦協定を締結し事態の沈静化が図られましたが、通州事件や第二次上海事変等で対立は決定的となり、全面戦争へと突入してしまったのです。この様な情勢下、共産党と手を組んで迄して「抗日」(対日全面対決)に固執する蒋介石に見切りを付け、対日和平を一日も早く実現し、支那国内の秩序を取り戻そうとしたのが、同じ国民党にありながら反蒋介石派の重鎮、汪兆銘であり、実際に彼が組織したのが、日本が「支那における正統政権」として承認した南京国民政府だったのです。
話が長くなってしまいましたが、当時の「中華民国」とは、かつての五胡十六国時代(316〜439)や五代十国時代(907〜960)と同様の乱世であり、到底「統一国家」として体をなしてはいなかった訳です。又、当時の列強も、米国が国民党の蒋介石を、英国が山西軍の馮玉祥を、ソ連が共産党の毛沢東を、そして、日本が汪兆銘を、と言った具合にそれぞれ異なった勢力を支援していた訳で、列強諸国の思惑も複雑に加わり、正に「大国の代理戦争」と言った様相を呈していました。更に言えば、「中華民国」は、内戦時代のアフガニスタン同様、各勢力の離合集散が繰り返され、一体誰(どの勢力)が国家を代表する「主権者」(正統政府)なのかも分からないと言った状態で、当時の日本が「支那における正統政権」として承認していた汪兆銘政権と締結した様々な約束も、一歩、同政権の支配地域を出れば、何らの効力も持たないと言った有様だった訳です。
つまり、「中華民国」とは、全土に対する統一した統治権を持ち、責任を持って諸外国と外交交渉をし、国家間で締結された各種条約を責任を持って遵守履行出来るだけの実力を持った「統一政府」が無かった訳で、より具体的に言えば、「中華民国」と言う鍋(国家)の蓋を開けてみたら、中はどの食材(勢力)が主役なのかも分からない様な「闇鍋」だったとでも言えば良いでしょうか? 国家主権不在の乱世 ── 「中華民国」を評する時、これが一番当を得ている様に思うのです。そして、その国家主権不在の「中華民国」 ── 当時の支那によって言い様に振り回されたのが、支那事変の一方の当事者として、泥沼に陥った隣国・日本だった共言えるのです。(了)
読者の声 (メールマガジン ≪ WEB 熱線 第1179号 ≫ 2009/5/22_Fri ― アジアの街角から― のクリックアンケートより)